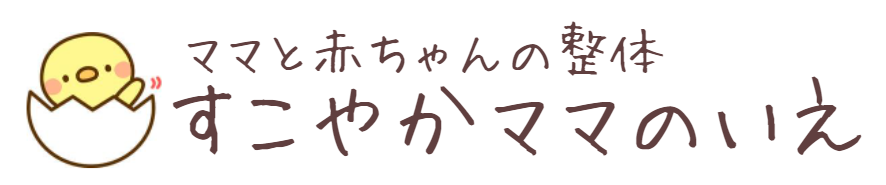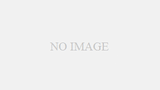今夜は関東地方でも雪が降るようですね。
すでに寒空が上空に広がっていて、見たただけで寒さを感じます。
雪が降ると車の運転が怖いので、極力したくないのですが
保育園は休ませればいいとしても
小学校は遅れてでもやるので、結果送っていくことがあり、
たくさん雪が降った昨年は恐怖でした。
おまけに子供の社会見学と大雪の日がかぶって延期になり、
お弁当の日が増えたことも地味に嫌でした。

栃木県は坂道が多く雪が積もるとスタッドレスタイヤでも登れなくなって立ち往生渋滞が発生します。
実家は坂の上にあるため、降るかどうかわからない雪のために車は4WD必須でした。
若い?頃、助産師になるために青森県弘前市の助産師学校に進学しました。
青森県の津軽地方です。
当たり前ですが雪いっぱいです。
私がいた1年間はそれでも例年よりは少なかったようですが、
同じ国?と思うほど冬の間は雪が消えることがなく、
根雪の上にさらに新雪が積もって超危険な道ができたり、
車道は除雪しているのに歩道は手つかずで車道と歩道の境目がわからない、
雪を端に寄せるために道幅が狭くなる、
うっかり軒下を歩くと巨大に育ったつららが頭に刺さりそうになって危ない、
1m先が見えないような吹雪で、関東だったら即休校になるような天気でも当たり前に授業があって
学校までの道のりで遭難するんじゃないかと思ったりなど、
関東地方でぬくぬくと育った私には考えられないようなデンジャラスな日常生活となりました。
管理の行き届いたアパートだったので雪かきをすることはほとんどありませんでしたが、
かいてもかいても翌日にはまた積もっているのを見ると複雑な気持ちになりました。
学生基本の移動手段である自転車は危なくて乗れなくなり、
買い物などすべて徒歩移動になります。
それでもツワモノ地元民がよたよたと自転車で道路を通行していると見ている方が恐怖です。
なんせ間違って車道側に転びでもしたら即命がありませんので。
他にも、割と暖房器具備え付けが標準装備の賃貸住居が多いこと、
寒さ・結露対策で窓が二重構造になっていることなど、生活環境の違いを感じました。
ぶっちゃけ津軽弁が理解できなくて講義が聴き取れず
津軽弁のヒアリングから始まった学生生活も含めてありとあらゆることが未知の世界、つまり非日常でした。
でも、人間だんだんと適応していくもので、
わずか1年の滞在にも関わらず、若者の津軽弁ならなんとかヒアリングができるようになり(年配者は到底無理)、
日常会話では津軽弁トークも可能になりました(笑)。
うっかり東京の就職試験で出てしまうくらいには身に付きました。
気づけば、それは私の中で日常になっていました。
そんな経験をしているのだから、雪なんかへっちゃらでしょ、と言われることもあります。
が、その後東京で快適に生活、栃木に戻って栃木の生活にどっぷりつかっているうちに、
また私の中の日常が栃木県での生活に変わります。
そして、雪国での生活はあっという間に非日常に戻っていきました。
環境によって日常と非日常は入れ替わることがあります。
例えば、親と同居していて家事は母親がやってくれていた日常から一人暮らしになると、
はじめは非日常だったひとりでの生活が、慣れるにつれて日常になり、実家に帰省することが非日常になります。
これは環境に適応する力が関わっています。
環境が変わってもすぐにそれに馴染んでいける人も、
なかなかなじめずに、ついには体調を崩してしまう人もいます。
環境の変化に耐えられないとき、多くはストレスという言葉で表わされます。
ストレスに耐えられないときにできる対策は2つ。
①ストレスの原因を排除する
②ストレスに耐えられる抵抗力をつける
社会的に問題なければ①が簡単です。
でも、そうはいっても職場の上司が原因だからすぐ仕事やめますとは言えない人の方が多いものです。
そういうときに、体の土台(骨盤)を整えるとふんばりがきくようになります。これが②です。
骨盤が不安定だとお腹に力が入りにくくなり、物理的にふんばりが効かなくなります。
ふんばりがきかない体は防御力が低いのでダメージをくらいます。
天気の話からだいぶ遠いところにきてしまいましたが、
日常と非日常の入れ替わりをスムーズにするもしないも、土台の体が大切です。
学生は試験や進学、社会人は就職や部署の移動、新人の入職など、
これから春に向けて、年度を締めくくると同時に新しい生活に変わる、
新しい日常をつくる方も多くおられると思います。
春が来る前に、新日常に向けて土台を整えておくことは病気の予防や健康を目指すことと同じ意味です。
インフルエンザも流行っておりますので、ご自分の抵抗力と向き合ってみるのもよいのではないでしょうか。